よみもの
文献や関連サイトの内容紹介や、メンバーによるエッセイなど随時掲載していきます。
紹介コーナー
【03】特別寄稿:古典を飼いならす!? ―「100分de名著:デュルケーム 社会分業論」(NHK・ETV)出演始末 New!
芦田徹郎(甲南女子大学名誉教授)
「星の王子さま」のことから
NHK・ETVに、古今東西の「名著」とよばれる書物をわかりやすく紹介する「100分de名著」という番組(25分×4週)がある。この種のジャンルとしては珍しく、長年にわたって安定した視聴率を維持しているのだという。私は、今年2月のその放送で、デュルケームの『社会分業論』についての解説を担当する機会を得た。この企画が告知されると、コアな視聴者のSNSなどには(と言っても私自身はSNSをしていないので、知人からの2次的情報である)「社会学とは珍しい」「まさかのデュルケーム」「『自殺論』ではないの?」といった、その意外性を表明する声があがったようである。意外といえば、その最たるものは講師のキャスティングだったかもしれない。「アシダって誰?」「なぜアイツが?」といった疑問をもたれた向きも多かったのではないか。そのあたりの事情も含め、今回のイベントの経緯や、その経験をとおして考えたり感じたりしたことの一端を報告したい。
甲南女子大学を退職して現役生活にピリオドを打ち、もう10年近くになる。「職業としての学問」は鳴かず飛ばずに終わってしまったが、引退後の「趣味のお勉強」がおもしろく、また大学が引き続き研究紀要への投稿を認めてくれているので、家事雑事に加えて、本を読んだり、資料を調べたり、考え事をまとめたりして、けっこう研究活動?も忙しい。目下の主たる研究テーマは、フランスの作家サン=テグジュペリのあまりにも有名な物語『星の王子さま』の社会学的読解である。
王子さまが暮らす宇宙世界では、一つひとつの星に「王さま」「うぬぼれ屋(エンターテイナーか?)」「ビジネスマン」「街灯の点灯人」「地理学者」「酒びたり(失業者か?)」といった一つの地位が配分され、それぞれの星に一人っきりで住んでいる専門家が自分の役割を忠実に遂行している。もともと王子さまが住んでいた星はその手入れに従事する「庭師」の星のようであり、王子さまは庭師修業中の見習いと思われる。
ところが、この分業世界の構成員たちは、そろいもそろって「精神のない専門人」か「心情のない享楽人」(M.ウェーバー)ばかりなのだ。それぞれが自分の小さな星に閉じ籠って職務に没入しているものの、相互に交わることも関わることもなく、他者の仕事を理解したりリスペクトすることもない。したがって、それぞれが自分の社会的役割には極めて忠実であるが、「業務命令は業務命令だ、なにも理解する必要などない」という点灯人の言葉が端的に示すように、その職務にどんな社会的意義があるのかはよくわかっていない。それ故、一方では相互の「紐帯」あるいは「連帯」というものは存在せず、他方では誰もが自尊と自虐とのあいだを揺れ動いている。まさしく、「社会学的想像力」(ミルズ)が欠如した「ホモ・ソシオロジクス」(ダーレンドルフ)ばかりなのである。
他方、庭師見習いの王子さまは、いっときは一本の美しい「花」(バラ)の手入れに夢中になるが、やがて「花」が自分の思い通りにならないことで挫折し、ひとり不全感と孤独を抱えて「なすべきことoccupation」を探す旅に出る。しかし、その途次教えを乞うため立ち寄った星々の住人たちは、上記のように自分の役割に埋没している「ヘンなおとなのひと」ばかりであり、王子さまの探求の志に応えてくれる者は誰もいない。それでも、最後にたどり着いた地球で出会ったキツネから、「絆を結ぶ」ことの大切さを学び、かつてその世話に没頭したバラとの愛と責任に目覚めることになる。しかし、その絆は二人だけの狭い「親密圏」に閉じられ、「社会」からは孤絶しているように思える。「ヘンなおとなのひとたち」の世界のような「絆なき社会」は可能なのか、王子さまとバラとの関係のような「社会なき絆」は可能なのか…… (全文は こちら)
(2025.8.26記)
※本稿掲載にあたり、番組担当者の了解をえています。
【02】特別寄稿 プロブレマティークの深み
北垣 徹(西南学院大学)
フランス語を学び始めた大学生の頃、「プロブレマティーク」という語に妙に惹かれた記憶がある。この語はたんなる「問題」よりもかなり含みがあって、まさに問題含みの言葉だ。そのことを理解するまでにしばらく時間を要し、その意味ではとっつきにくい言葉だと感じもしたが、同時にこの語の含蓄の深みに魅了されたのも確かである。problématique (n.f.)は「問題提起」や「問題構成」、さらには「問題群」と訳されたりするが、ある問題の立て方や、他の諸問題との関連が重要視される。たんなる問題であれば、問題そのものよりも解答の方が重要視され、問題に対して正しい解答か誤った解答かが問われる。ところがプロブレマティークという場合、問題の方が重要視され、正しい問題か、間違った問題かが問われる。つまり適切に問題が提起され、構成されているかどうか、他の諸問題と適切な関連付けがなされているかどうかが問われるのだ。
プロブレマティークの側面に目を向けると、技術的・科学的な問題だと思われるものが、実は政治的・社会的・文化的な要因に根ざしているということが見えてくる。問題には様々な仮説や想定、担い手が含まれていることが分かる。短期的なスパンの問題だと思われたものが、実は長期的なスパンに根ざしていることが見えてきたり、問題に異なる価値観や競合するステイクホルダーが含まれることが明らかになったりする。つまるところ、プロブレマティークとしての問題とは、予め存在する単純な所与ではなく、つくり出され、更新されるべき何かであり、異質な諸要素を含む複雑な構成物である。
またプロブレマティークとしての問題は、それにたいする解答と密接な関連のなかにある。問題と独立して解答が与えられるのではなく、問題の中に、問題の立て方の中に、すでに解答の一部が含まれている。問題の立て方が、すでに解答の在処を示唆している。政治的な問題の立て方は、政治的な問題の解決を促し、経済的な問題の立て方は、経済的な問題の解決を促す。また誤った問題からは、どんなに頑張っても誤った解答しか導くことができない。不毛な二者択一の問題からは、望ましき解答は得られないように。
昨年末に拙著『社会学の問い』(中川書店、2022年)を上梓するに当たり、タイトルを模索するなかで思い出されたのはこのようなことだ。本書の冒頭の章で「社会問題」に触れているが、それはあれこれの社会諸問題を指すのではなく、社会の存立そのものに関わる問題である。それは19世紀の歴史的文脈のなかではじめて問われるようになる。社会問題はまさしくプロブレマティークとして問われなければならない。大家族や地域共同体、同業組合などの中間団体が解体し、強力な国民国家とバラバラの諸個人が対峙するという状況の中で、いかにして新たな社会的な紐帯を再構築するのかという問題が社会問題であり、社会学という学問そのものがそうした問題に解答を与えようとする試みの中で成立する。つまり社会学は社会問題というプロブレマティークの中に含み込まれているのだ。
デュルケームの場合、社会問題は人々をある種の自殺に向かわせるアノミーのように、欲望や情念の無規制状態として捉えられる。他方でデュルケームにとって社会生活の本質とは、象徴や表象にある。つまり社会とは集合的表象によって構成される。アノミーとは、本質的に無際限な人々の欲望や情念を適切に導くための表象が欠けた状態であり、かつてであれば宗教を通じてそうした表象が作られていた。アノミーの克服、つまり社会問題の解決とは、宗教を通じてではないかたちで欲望や情念に規制をもたらす集合的な表象を構築することによってなされる。デュルケームにとってその作業の任は、かつての同業組合に代わる職能集団に託される。職能集団は経済活動の単位であるばかりでなく、政治的な単位(地域による選挙区ではなく、職能集団が選挙区となる可能性が示唆される)でもあり、また機能の縮小した家族に替わる社会的単位でもある。かくしてデュルケームにおいては、新たな中間団体としての職能集団こそが、人々の欲望や情念を適切に導く枠組みとなり、社会問題の解決策となるのだ。
この文章を読む者はデュルケームの熱心な読者であろうし、また拙著でもこの点については十分に言及しているので、これ以上ここでデュルケームの論を敷衍する必要はないだろう。むしろここで触れておきたいのは、このようなデュルケームの著作に含まれプロブレマティークを読み取る方法を、私はむしろデュルケームには拠らないところから引き出してきた点である。例えばそうした典拠とは、バシュラールやカンギレームであり、マルクスを読むアルチュセールであり、ベルクソンを論じるドゥルーズである。とりわけアルチュセールの、イデオロギーとの関連でプロブレマティークを論じる議論には強い影響を受けた。イデオロギー同様、プロブレマティークは対象の内容そのものよりも、そうした内容の提起の仕方に関わる。人はプロブレマティークについて考えるのではなく、プロブレマティークにおいて考えるため、それを意識するのは難しい——それはイデオロギーについて考えるよりも、イデオロギーにおいて考えるために、それを意識するのが難しいのと同様である。
しかし拙著の中では、アルチュセールへの言及はなく、バシュラールやカンギレームへもない。その本のもとになった本について、その本のなかでは案外言及されないものである。やはり拙著の中で言及されていないが、『社会学の問い』というタイトルは馬場靖雄の快著『社会学のおしえ』(ナカニシヤ出版、1997年)に負っている。馬場さんは彼の著書のタイトルが高橋悠治の『音楽のおしえ』に負っていることを、当該書の冒頭で明記しているけれども。かくして、明示的なかたちであれ、暗黙のかたちであれ、書物はさまざまな依存関係でつながっている。その思いもかけない関係を辿ること、つまりある書を読みながら、その書とは一見遠く離れているように思われる書を想起することが、読書という行為の目指すべきところだろう。
(2023.5.1記)
・本文章は、『社会学の問い』(中川書店, 2022年)の刊行に際し、著者でデュルケーム/デュルケーム学派研究会会員でもある北垣徹先生にご寄稿いただきました。
【01】いまここにある過去 小川伸彦
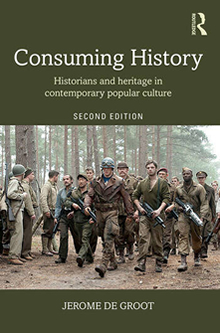
デュルケームの聖なるものに関する視点などを活かしつつ、これまで<文化遺産の社会学>に関心を寄せてきた筆者ですが、この科研費研究を進めるうちに、いまさらながら気づいたことがひとつあります。それは、文化遺産論というものが、モノ論やシンボル論、アイデンティティ論や他者論などであると同時に、大きくいえば過去表象論でもあるということです。
そういう視点で海外文献を渉猟(というほどでもないですが)してみると、現代人の過去観についてや、文化やメディアにおける過去のありかたについての研究の蓄積がかなりあることがわかってきました。そこで、この分野を手掛けておられる方には周知かと思いますが、入手できた先行研究を3冊、コンパクトに紹介してみたいと思います(邦題はいずれも仮訳)。
まず1冊目は、Jerome de Grootによる『歴史を消費する』です(2009年に刊行後、2016年に第2版)。紹介文には「本書が検討するのは、同時代のポピュラーカルチャーにおいて"歴史"というものがどのように働いているか、である。コンピューターゲームから昼のテレビ番組まで、文化にかかわるものを幅広く分析することを通じて、本書は、いかに社会が歴史を消費しているか、および、この種の消費を読み解くことが大衆文化と表象に関わる諸問題を理解するのにいかに役立つかを探索する」とあります。その構成は、<第1部:ポピュラー歴史家、第2部:デジタル化された歴史、第3部:歴史を演じる/歴史で遊ぶ、第4部:テレビの中の歴史、第5部:文化ジャンルとしての「歴史的なもの」、第6部:物質的な歴史>となっていて、包括的な目配りのよさが特徴です。ちなみに、文化遺産やミュージアムについては、最後の第6部で触れられています。
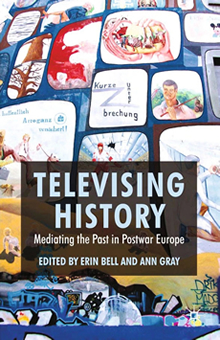
2冊目は、分析対象を特にテレビに絞ったE. Bellと A. Grayの編集による『歴史のテレビ化―戦後ヨーロッパにおいてメディア化される歴史』(2010年刊)です。全16章に序文と結論がついたバラエティーに富む内容は、欧州各国の事例をカバーしており、テーマも、歴史ドキュメンタリー論や伝記番組論・歴史ドラマ論など多彩です。たとえばフランスにおけるナポレオンの扱われ方を論じた章を担当したIsabelle Veyrat-Massonは、研究の視座として、「テレビというものは、共有されたナショナルな語りの構築において基軸的な役割を果たす。そして、パブリックな空間と文化的圏域との関係の特質に影響を与える」(p. 97)としています。なお、編者による序文の冒頭には「過去表象の分析は急速に発展しつつある研究分野である」とあり、文献表には1970年代のものもふくめさまざまな先行研究が掲げられている点も参考になります。
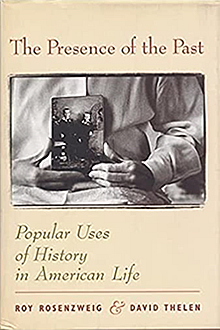
最後に紹介したいのは、R. RosenzweigとD. Thelenによる『過去の現・在:アメリカの生活におけるポピュラーな歴史利用』です。本書の最大の特徴は、すでに紹介した2冊のように文化コンテンツの中に歴史や過去の用いられ方を探るのではなく、さまざまな属性やバックグラウンドをもつ一般の人びとに、生活や意識のなかでの歴史の位置づけを直接聞き取り調査している点にあります。たとえば過去をめぐる行為や経験については、<過去12か月の間に次のことをしましたか?>として、「家族や友達と写真を見たか/思い出を残すために写真やビデオを撮ったか/過去に関する映画またはテレビ番組を見たか/歴史博物館や史跡を訪れたか/家族の歴史を調べたり、家系図づくりをしたりしたか/日記を書いたか」などの設問がなされています。歴史的知識の源泉として信頼できるのはなにか/だれか、といった問いもあります。調査が実施されたのは1994年で、刊行された1998年からもすでに20年以上が経っていますが、調査に関する情報をフォローアップするサイト(2022.11.07最終閲覧)は今も健在です。
* * *
まだじっくりとは読み込めているわけではありませんが、過去や歴史をめぐる文化コンテンツとその受け手との関係をどのように描きだしているかがひとつのポイントだと考えています。文化コンテンツが人々の意識や感情を作り出すいっぽうで、人々の意識や感情が特定の文化コンテンツを生み出す(=制作を促す)……。そんな相互的・循環的な影響関係のあり方を、データに基づいて論じているような研究に出会いたいものです。そうすれば、ある社会の集合意識や情動のあり方が、過去に関する集合表象とどのように関わっているかも少しずつみえてくることでしょう。
(2022.11記)
【書誌情報(紹介順)】
- De Groot, Jerome 2016, Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture (2nd edition), Routledge.
- Bell, Erin and Ann Gray (eds.) 2010, Televising History: Mediating the Past in Postwar Europe, Palgrave Macmillan.
- Rosenzweig, Roy and David Thelen 1998, The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life, Columbia University Press.
エッセイなど
【04】エヴァ・イルーズ氏来日連続セミナー開催記 山田陽子 NEW
本科研では、2024年3月に、エヴァ・イルーズ先生をお招きして来日連続セミナーを開催しました。
- 第1回セミナー「感情・集合意識・ポピュリズムー現代社会における政治的分断をいかに考えるか Émotion, conscience collective et populisme : Comment penser les divisions politiques dans la société contemporaine ?」 「恐怖・嫌悪・恨み・国家への愛 Peur, dégoût, ressentiment, amour de la nation」(2024年3月11日・日仏会館)
- 第2回セミナー「感情・親密性・資本主義-愛の終焉とエモディティ(感情商品)Émotion, intimité et capitalisme:La fin de l'amour et "l'émodité"」(2024年3月13日・大阪大学中之島センター)
東京と大阪、各日程ともに早期満席になる盛況でした。一般の方も多くご参加になりました。
第2回セミナーの開催報告はこちらをご参照ください。
イルーズ先生とは、東京では日本の近現代史が分かる博物館に行きました。京都では、寺院でお庭を眺めながら抹茶と和菓子を楽しみ、歌舞伎を鑑賞しました。ファッションがお好きとのことで、ショッピングもご一緒しました。何気ない会話の節々に観察眼の鋭さが光る、素敵な先生でした。大きな知性と数日対話することができ、有意義な招聘であったと思います。
なお、第1回セミナーは当日の講演内容の全訳が、第2回セミナーについては詳細な議論の記録が、それぞれ2024年度中に学術雑誌に掲載される予定です。
(2024.11.6.記)
【03】Impressions du Japon Gildas SALMON (CNRS, EHESS)
Les journées d’études auxquelles j’ai eu la chance de participer lors de mon séjour au Japon en février-mars 2023 ont été l’occasion d’une double découverte. Tout d’abord, j’ai découvert l’existence d’une véritable école japonaise travaillant sur l’histoire de la sociologie et de l’anthropologie française de tradition durkheimienne. Même si la présence de doctorants japonais au LIER-FYT depuis une dizaine d’années m’avait déjà donné un aperçu de ces recherches, j’ai pu grâce à ce séjour prendre la mesure de l’importance du réseau de chercheurs travaillant en ce sens, et de l’ampleur du programme de traduction des textes durkheimiens vers le japonais.
Leur connaissance très fine des textes de Durkheim et de ses élèves a donné lieu à des échanges passionnants à propos des hypothèses que j’étais venu présenter à l’université de Nara sur le devenir de l’analyse des mythes dans l’école durkheimienne, chez Granet et Lévi-Strauss, et à Tokyo sur la crise de l’évolutionnisme dans la sociologie de la seconde moitié du XXe siècle.
La deuxième découverte qu’a permis ce séjour est celle du Japon, où je venais pour la première fois. Le temps dont je disposais ne m’a permis d’avoir qu’un aperçu rapide de son patrimoine historique (à Nara et Kyoto en particulier) et de son urbanisme le plus moderne (à Tokyo notamment), mais la confrontation à un pays ayant connu une trajectoire de modernisation autonome, différente de celle de l’Europe (même si les interactions ont été nombreuses), a été une expérience fascinante. Je n’ai cessé de me dire, tout au long de ce séjour, à quel point l’histoire des sciences sociales entendues comme formes de réflexivité sur les dynamiques de transformation des sociétés modernes à laquelle nous travaillons au LIER-FYT pourrait être enrichie par la comparaison du cas japonais avec les cas français, allemand, britannique et américain, mieux connus en Europe.
Les discussions engagées lors du colloque consacré à cette question de la modernité à la Maison française de Tokyo m’ont donné un premier aperçu des bénéfices qu’on peut attendre d’un tel croisement des points de vue, et je ne peux qu’espérer que la collaboration ainsi engagée se poursuive et se développe à l’avenir.
日本の印象
ジルダ・サルモン Gildas SALMON
(国立科学研究センターCNRS・社会科学高等研究院EHESS)
白鳥義彦(神戸大学) 訳
2023年2月から3月にかけての日本滞在時に参加する機会を得たシンポジウムは、二重の発見の場となりました。まず、デュルケームの伝統を受け継ぐフランスの社会学および人類学の歴史について研究する、真の学派が日本に存在することを発見しました。ここ10年来、LIER-FYT〔訳注:Laboratoire interdisciplinaire d’études sur les réflexivités - Fonds Yan Thomas、反省性に関する学際研究室―ヤン・トマ文庫。社会科学高等研究院EHESSの、サルモン氏が所属する研究室〕に日本人の博士課程学生が在籍していたことで、こうした研究が行われていることをすでに知ってはいましたが、今回の滞在のおかげで、こうした方向で研究を進める研究者ネットワークの重要性と、デュルケームのテクストの日本語への翻訳プログラムの広がりを認識することができました。
デュルケームおよびその門弟たちのテクストについての非常に精細な彼らの知識は、私が奈良女子大学で行った、グラネおよびレヴィ=ストロースに見られるデュルケーム学派における神話分析の転変についての、また東京で行った、20世紀後半の社会学における進化主義の危機についての仮説をめぐる、大いに心動かされる意見交換をもたらしました。
この滞在によって可能となった第二の発見は、私が初めて訪れた日本についてです。時間が限られていたために、歴史的遺産(特に奈良および京都における)と最も現代的な都市計画(とりわけ東京における)とをざっと概観することしかできませんでしたが、(たとえ数多くの相互作用があったとしても)ヨーロッパとは異なる、自律的な近代化の道程をたどった国と対峙することは、魅力的な経験でした。この滞在を通じて私はずっと、私たちがLIER-FYTで研究している、現代社会の変容の力動についての反省性の諸形態として理解される社会科学の歴史は、ヨーロッパでより知られているフランス、ドイツ、イギリス、アメリカの事例と日本の事例との比較によっていかにより充実したものになり得るのだろうかと、絶えず考え続けていました。
モダニティへのこの問いを主題とする、東京の日仏会館でのシンポジウムに際してなされた議論は、視点のこのような交差から期待できる利点についての最初の着眼を与えてくれたのであり、そして私はこのように関わり合う協力が将来にわたって継続され発展することを願わずにはいられません。
【02】ストリートピアノ雑感 川本彩花
昨年12月、第26回奈良女子大学社会学研究会において、「社会・地域と関わる音楽プロジェクトをめぐる研究動向について」の研究報告を行った。この研究会は、対面とオンラインとを併用したいわゆるハイブリッドのかたちで開催され、私は対面にて参加・研究報告を行うため、会場である奈良女子大学を訪れた。ここ数年間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、同研究会はオンラインでの開催が続いており、対面を取り入れての開催は久々であった。私個人としても、奈良を訪れたのは約3年ぶりとなり、懐かしいような、しかしどこか新しくなったような駅やまちの様子などを目にし、感慨深い気持ちになった。
上記のような研究報告に加えて、現地調査も進めているのであるが、そのようななかで最近、各地の駅やまちなかなどにおいて、「ストリートピアノ」を見かけることが増えたように思う。公共スペースに設置され、誰もが自由にふれて弾くことのできるピアノである。なかには、カラフルに装飾・ペイントされたピアノや、華やかな雰囲気を醸し出すグランドピアノなどもある。また、演奏され鳴り響いているピアノや、演奏されるのを静かに待っているピアノなど、そこには様々な光景があり、興味・関心をもって見ている。もっとも、「ストリートピアノ」を見かけることが増えたように思うのも、この科研費研究において、とくに「未来への情動:活路としての音楽」の研究テーマに取り組んでいるため、こうした音楽にかかわるモノ・コトに目が留まりがちなところもあるのかもしれない。(なお、実際には、コロナ禍において、一時的にせよ演奏不可となったケースも少なくないようである。)
誰もが自由にふれて弾くことのできる「ストリートピアノ」であるが、それでは、こうした「ストリートピアノ」の設置が各地で進められるということは、社会学的に考えるとどのようにとらえられるのだろうか。あるいは、そこにはどのような可能性が考えられるのだろうか。たとえば、日常生活のなかにおいて、「ピアノ」という楽器に実際にふれる、弾いてみる、楽しむといった機会が広がり、ひいては、音楽文化にさらに身近なかたちで接することができるといったことがまず挙げられるだろうか。
そのようなことにも思いをめぐらせつつ、この「ストリートピアノ」をめぐる光景は、いま取り組んでいる「未来への情動:活路としての音楽」の研究テーマを深めていく際にも示唆を与えてくれるもののひとつであるようにも思えるのである。
(2023.2.1記)
【01】社会を成り立たせるもの 白鳥義彦
「同じ信仰をもつことなしに社会は繁栄し得ず、というより、そうでなければ社会は存続しない。なぜなら、共通の観念なくして共通の行動はなく、共通の行動なくしては、人間は存在しても社会はないからである。社会が存在するため、それ以上にその社会が繁栄するためには、すべての市民の精神が常にいくつかの主要な観念によってまとめられ、一つになっていなければならない」。エミール・デュルケーム(1858年-1917年)による語りとしても通じそうなこの言葉は、実際はアレクシ・ド・トクヴィル(1805年-1859年)が『アメリカのデモクラシー』(松本礼二訳、第二巻(上)、26頁、2008年、岩波文庫。原著刊行は、第一巻が1835年、第二巻が1840年)で述べているものである。社会がいかに成り立つかという問題は社会学における根本的なもので、それぞれの論者がそれぞれの立場から論を展開しているが、社会が存在するためにはその成員が共有するものが必要だという、集合意識にも通じるここに見る視点は、デュルケームとトクヴィルに共通しているものである。社会学の歴史のなかでは、ともに中間集団の重要性を論じた者としてこの二人を位置づけることができるが、社会がいかに成り立つかということに対する根本的な観点においても両者はその立場を共にしている。
ヨーロッパという「旧世界」とりわけフランスとの対比のなかで、「新世界」という、階級のない平等で民主的なアメリカ社会のあり方を鋭く観察し、記述したトクヴィルは、大衆社会について先駆的に論じた者としてもとらえることができる。例えば、のちの印象派の隆盛を予見するような、「ルネッサンスの画家たちは、通例、自分を超えるところやはるか昔の時代に彼らの想像力を大きく羽ばたかせる壮大な主題を求めた。われわれの時代の画家たちはしばしば、彼らが始終目にしている私生活の細部を正確に再現することに才能を傾け、自然界に原型があり余るほどある小さな対象をあらゆる側面から写している」(同、96頁)という洞察も大変興味深い。「印象派」の名前の由来となる、クロード・モネによる「印象・日の出」が描かれたのは1872年なので、この言葉が公刊されたのはそれよりも30年以上も先立っていることになる。大衆社会や、そこでの情動のあり方という観点においても、トクヴィルの議論には多くの示唆を見出すことができる。
(2022.11記)